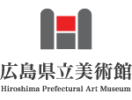所蔵品
所蔵品
刺繍布(スザニ)
スザニは、ペルシア語で針という意味のスザンから派生した言葉で、刺繍または刺繍したものの意で、さまざまな素材、様式のスザニを中央アジア全域で見ることができる。主にウズベク人やタジク人によって制作され、中央アジアの広い地域で壁掛けや掛け布に使われる。なかでもミヒラーブ(モスクの礼拝堂にある聖地メッカの方向を示すアーチ型の壁龕)を表したものは礼拝布として用いられる。
つくりかたは次のようである。まず、縫い合わせていない細幅の木綿布や絹布に下絵を線描し、次に一族の女性たちが分担して刺繍し、最後に刺繍した数本の布を縫い合わせて完成させる。そのため、時には布の継ぎ目で刺繍糸の色が違ったり、刺繍の刺しかたが異なったり、下絵どおりに刺繍していない例も散見される。ウズベクやタジクでは、女の子が幼い頃からスザニを準備し始め、かつて、婚礼の際に花嫁は数枚から十数枚を持参した。
この作品がつくられた地であるヌラタは現在のウズベキスタンのナヴォイ州に位置し、早くも紀元前4世紀のアレクサンドロス大王時代に記録が現れる古い都市で、この作品のように優雅で華麗な草花文のある様式で知られる。スザニの様式は地域によって異なり、タシケント、サマルカンド、ブハラ、シャフリサブスなど都市名を冠して称されてきたが、現代では人気のある様式をまったく別の地域でも制作することがあり、様式によって制作地を推測することは難しくなった。
現代では簡略化が進み、バザール(市場)で買ったり、ミシン刺繍のスザニを注文したりする風潮が広まってきた。一方で、手刺繍によるスザニ制作は商業的に息を吹き返し、女性たちは家族のためでなく内職として刺繍するようになり、輸出用スザニの生産が伸びている。グローバル化のなかで生活様式や価値観が変化する現代にあっても、伝統文化の再評価、民族の誇りとしてのスザニの存在は大きい。
つくりかたは次のようである。まず、縫い合わせていない細幅の木綿布や絹布に下絵を線描し、次に一族の女性たちが分担して刺繍し、最後に刺繍した数本の布を縫い合わせて完成させる。そのため、時には布の継ぎ目で刺繍糸の色が違ったり、刺繍の刺しかたが異なったり、下絵どおりに刺繍していない例も散見される。ウズベクやタジクでは、女の子が幼い頃からスザニを準備し始め、かつて、婚礼の際に花嫁は数枚から十数枚を持参した。
この作品がつくられた地であるヌラタは現在のウズベキスタンのナヴォイ州に位置し、早くも紀元前4世紀のアレクサンドロス大王時代に記録が現れる古い都市で、この作品のように優雅で華麗な草花文のある様式で知られる。スザニの様式は地域によって異なり、タシケント、サマルカンド、ブハラ、シャフリサブスなど都市名を冠して称されてきたが、現代では人気のある様式をまったく別の地域でも制作することがあり、様式によって制作地を推測することは難しくなった。
現代では簡略化が進み、バザール(市場)で買ったり、ミシン刺繍のスザニを注文したりする風潮が広まってきた。一方で、手刺繍によるスザニ制作は商業的に息を吹き返し、女性たちは家族のためでなく内職として刺繍するようになり、輸出用スザニの生産が伸びている。グローバル化のなかで生活様式や価値観が変化する現代にあっても、伝統文化の再評価、民族の誇りとしてのスザニの存在は大きい。
| 名称 | 刺繍布(スザニ) ししゅうふ(すざに) |
|---|---|
| 作者名 | ヌラタ ヌラタ |
| 時代 | |
| 材質 | 木綿、絹糸、刺繍 |
| サイズ | 253.0×172.0 |
| 員数 | 1枚 |
| その他の情報 | |
| 指定区分 | |
| 分野 |