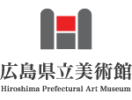所蔵品
所蔵品
内海の春
【作品解説】
平山郁夫は、画業の初期に日常の生活感覚を反映した作品を幾つか残しています。故郷・生口島の風俗をテーマにした本作もその一つです。本作では、畑仕事の合間、くつろいだ姿で休憩をとる農婦たちの間に交じる一人の少女を描いています。その姿は、太陽の恵みをたっぷりと浴びるミカンの樹と共に、故郷の風土と親しき人々への慕情を象徴しているように思われます。
【作家略歴】
1930(昭和5) 広島県豊田郡瀬戸田町(現尾道市)に生まれる
1945(昭和20) 学徒勤労動員中の広島陸軍兵器支廠で被爆
1947(昭和22) 東京美術学校(現東京芸術大学)に入学
1952(昭和27) 同校を卒業後、新制となった東京芸術大学副手に就任。前田青邨に師事
1953(昭和28) 第38回院展《家路》ではじめて入選
1959(昭和34) 被爆の後遺症に悩まされる中、第44回院展《仏教伝来》で入選
1962(昭和37) 第47回院展《受胎霊夢》《出現》で受賞。東西宗教美術の比較のために渡欧
1966(昭和41) 東京芸術大学第1次オリエント調査団に参加
1968(昭和43) はじめてアフガニスタンから中央アジアに至るシルクロードを取材
1973(昭和48) 東京芸術大学教授に就任
1989(平成元) 同大学長に就任
1998(平成10) 画業50年展を開催。文化勲章を受章
2000(平成12) 奈良、薬師寺玄奘三蔵院伽藍「大唐西域壁画」を完成
2001(平成13) アフガニスタン、バーミアン大仏の破壊について抗議声明を発表
2009(平成21) 東京都中央区の病院にて没
平山郁夫は、画業の初期に日常の生活感覚を反映した作品を幾つか残しています。故郷・生口島の風俗をテーマにした本作もその一つです。本作では、畑仕事の合間、くつろいだ姿で休憩をとる農婦たちの間に交じる一人の少女を描いています。その姿は、太陽の恵みをたっぷりと浴びるミカンの樹と共に、故郷の風土と親しき人々への慕情を象徴しているように思われます。
【作家略歴】
1930(昭和5) 広島県豊田郡瀬戸田町(現尾道市)に生まれる
1945(昭和20) 学徒勤労動員中の広島陸軍兵器支廠で被爆
1947(昭和22) 東京美術学校(現東京芸術大学)に入学
1952(昭和27) 同校を卒業後、新制となった東京芸術大学副手に就任。前田青邨に師事
1953(昭和28) 第38回院展《家路》ではじめて入選
1959(昭和34) 被爆の後遺症に悩まされる中、第44回院展《仏教伝来》で入選
1962(昭和37) 第47回院展《受胎霊夢》《出現》で受賞。東西宗教美術の比較のために渡欧
1966(昭和41) 東京芸術大学第1次オリエント調査団に参加
1968(昭和43) はじめてアフガニスタンから中央アジアに至るシルクロードを取材
1973(昭和48) 東京芸術大学教授に就任
1989(平成元) 同大学長に就任
1998(平成10) 画業50年展を開催。文化勲章を受章
2000(平成12) 奈良、薬師寺玄奘三蔵院伽藍「大唐西域壁画」を完成
2001(平成13) アフガニスタン、バーミアン大仏の破壊について抗議声明を発表
2009(平成21) 東京都中央区の病院にて没
| 名称 | 内海の春 ないかいのはる |
|---|---|
| 作者名 | 平山郁夫 ヒラヤマ・イクオ |
| 時代 | 昭和29年 |
| 材質 | 紙本彩色 |
| サイズ | 145.0×208.0 |
| 員数 | |
| その他の情報 | |
| 指定区分 | |
| 分野 |